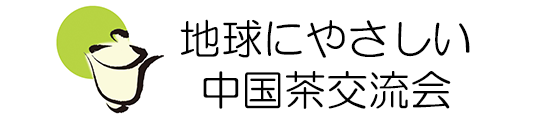【第21回 講演会】台湾山茶を追って
講演会「台湾山茶を追って」
近年台湾のみならず、海外のお茶好きからも注目されている台湾山茶ですが、その命名は日本人?その定義とは?
最近訪れる人が増えた高雄六亀。
6年前に現地で原住民から聞いた話とは?そして現在の六亀山茶事情は?
台湾大学に90年間保存されている山茶の標本(1935年第5代製茶試験場長谷村愛之助及び南投県魚池で最初に紅茶を作った持木壮造が発見)を見てワクワクし、その原木を探して険しい山を登ってみると、先人の偉大さが良く分かります。
更に日本に渡った台湾山茶を探して三重県亀山を訪ね、その歴史的背景を探ってみました。
最後に「なぜ今台湾山茶なのか?」を簡単に考察します。
※講演会では、お茶の試飲はございません。
実行委員会より
台湾の山中に自生している山茶が最近、注目を集めています。
その血筋は紅玉(台茶18号)や山蘊(台茶24号)などに引き継がれているほか、生産者や茶人の間でも山茶に可能性を感じている方もいらっしゃるようです。
山茶をキーワードに台湾のみならず日本の各地を巡ったお話を聞いて、これからの山茶を考えるヒントにしていただければと思います。
【時 間】2025年11月22日(土) 16:00~17:30
【講 師】須賀 努 先生
ブログ:茶旅ーアジア茶縁の旅
お茶をキーワードに旅をする茶旅を始めて25年。
ここ10年は茶の歴史に焦点を当て、誰も知らない茶歴史を自らの脚で探し歩いて執筆している。
これまで日本をはじめ、台湾、中国、香港、東南アジア、南アジア、ロシアなど20数か国で数百の茶旅を重ね、雑誌で発表、講演活動を行ってきた。
日本台湾交流協会の雑誌交流に『台湾茶の歴史を訪ねる』、静岡県茶業会議所の専門誌「月刊茶」に連載した他、人民中国『茶を通してみる華僑・華人の歴史と現在』で茶商の末裔から華人を読み解くなど、茶にまつわる多方面の歴史を考察している。
現在は東方書店Web「アジアを茶旅して」、CKRM中国紀行などで更に深い茶旅、茶のエピソードを連載している。
【会 場】地球にやさしい中国茶交流会 講演会場(4階第1会議室)
※メイン会場と別フロアですのでご注意ください。受付は直接、講演会場にお越しください。本会場への入場受付前でも参加いただけます。
【参加費】4,000円
【定 員】24名
2025年11月1日(土)21時より予約受付開始
【予約フォーム】以下のフォームをクリック